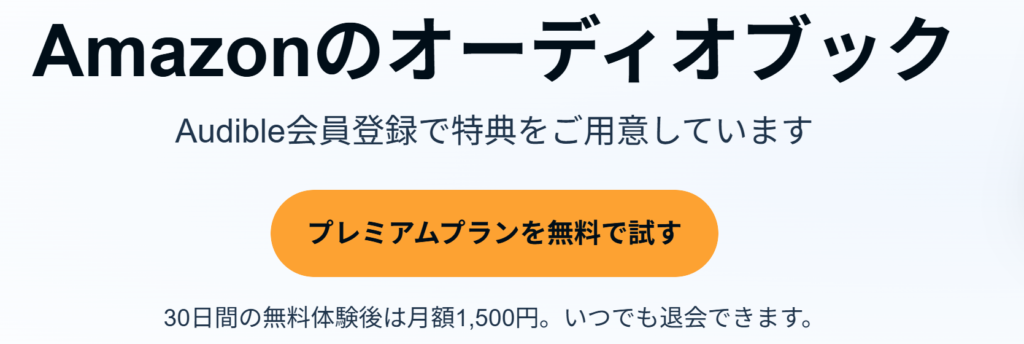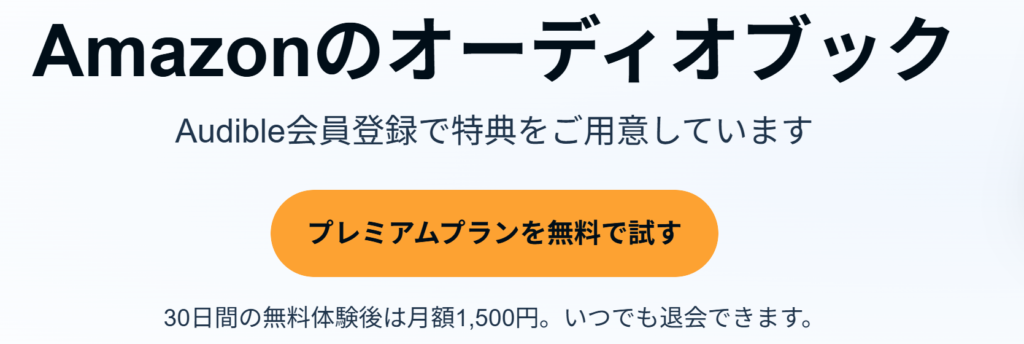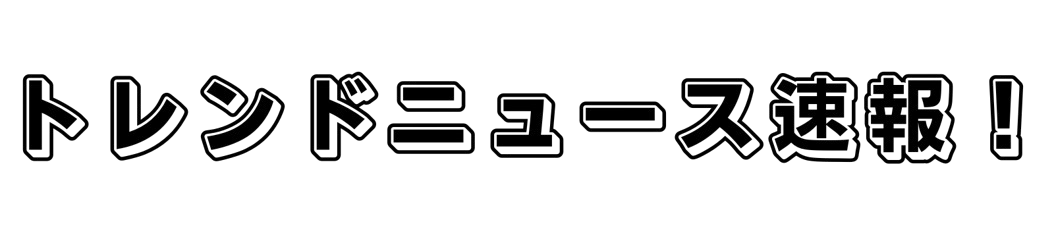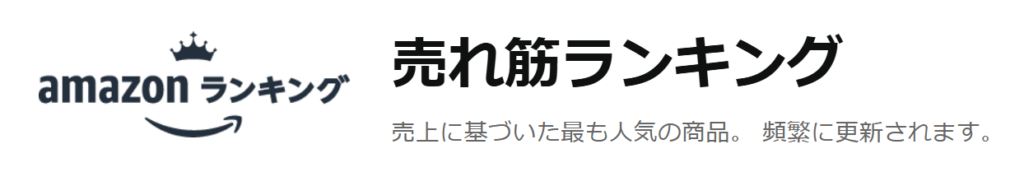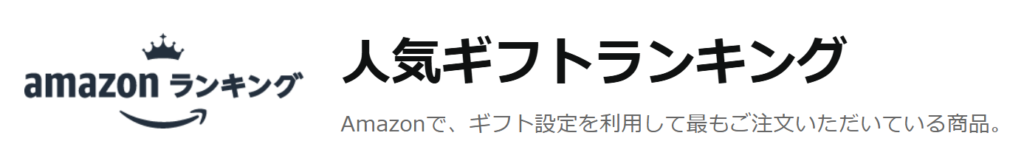8月21日午前、業務用エレベーターに首を挟まれた男性が見つかり、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。
なぜ、このような事故が発生したのでしょうか。
事故の概要や事故原因を検証していきたいと思います.
事故の概要

8月21日午前11時20分すぎ、大阪市住之江区新北島の工場で、「エレベーターに首が挟まれている」と同僚の男性から消防に通報がありました。
警察や消防が駆けつけると、業務用エレベーターに首を挟まれた50代とみられる男性が見つかりました。
病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。
過去の事例から見る事故原因
このような痛ましい事故は、残念ながら過去にも類似の事例が複数発生しています。
それらの事例を基に、今回の事故で考えられる原因を考察します。
詳細な原因は今後の調査で特定されることになりますが、一般的に以下の3つの要因が単独または複合的に絡み合って発生する可能性が指摘されています。
1. 不適切な使用方法(人的要因)
最も多く見られる原因の一つが、エレベーターの不適切な使用です。
特に、事故現場が工場であることから、荷物の昇降を主目的とした「荷物用エレベーター」や、より簡易な構造の「簡易リフト」であった可能性が考えられます。
- 荷物用エレベーターへの搭乗:
労働安全衛生規則では、荷物用エレベーターに労働者が搭乗することは原則として禁止されています(荷の積み下ろしのために乗り込む場合や、保守点検の場合などを除く)。
しかし、作業の効率を優先するあまり、荷物と一緒に作業員が乗り込んでしまうケースが後を絶ちません。
人が乗ることを前提としていないため、人が乗るエレベーター(乗用エレベーター)に比べて安全装置が簡素であったり、かご(ケージ)と建物の隙間が広かったりすることがあり、重大事故につながる危険性が高くなります。 - 乗り込み・乗り出し中の不意な動作:
かごが完全に停止する前に乗り込もうとしたり、あるいは、かごの中から身を乗り出したり、乗り場の外から上半身を入れて荷物を整理しようとしたりした際に、何らかの理由でかごが不意に昇降し、かごと建物の間に挟まれてしまうケースです。
今回の事故のように首が挟まれた状況は、このような乗り出し中の動作に起因する可能性が考えられます。
2. 安全装置の不備・故障(物的要因)
エレベーターには事故を未然に防ぐための様々な安全装置が備わっていますが、それらが正常に機能していなかった可能性も考えられます。
- ドアインターロック装置の不具合:
これは、乗り場のドアが完全に閉じていない状態では、かごが昇降しないようにするための極めて重要な安全装置です。
この装置が故障していたり、あるいは作業の利便性のために意図的に無効化(短絡・バイパス)されていたりすると、ドアが開いたままでもかごが動いてしまい、挟まれ事故の直接的な原因となります。
過去の多くの事故で、このドアインターロックの不備が指摘されています。 - その他の安全装置の故障や経年劣化:
かごが最上階や最下階を越えて動くのを防ぐリミットスイッチの故障や、ブレーキ系統の不具合、ワイヤーロープの劣化なども事故につながる可能性があります。
特に、設置から年数が経過した旧式のエレベーターの場合、部品の劣化や、現在の安全基準を満たす装置が設置されていないことも考えられます。
3. 維持管理・安全管理体制の問題
エレベーターの所有者や管理者には、安全な状態を維持するための管理責任があります。
- メンテナンス不足:
建築基準法や労働安全衛生法では、エレベーターの定期的な検査・保守が義務付けられています。
しかし、コスト削減などを理由に、必要なメンテナンスが適切に行われていなかった場合、前述のような安全装置の不具合や部品の劣化が見過ごされ、事故のリスクが高まります。 - 安全教育の不徹底:
作業員に対して、エレベーターの正しい使用方法や潜在的な危険性についての教育が十分に行われていなかった可能性も考えられます。
危険な使用方法が常態化し、作業員自身も危険性を認識しないまま作業を続けていたというケースも少なくありません。
今回の事故は、これらの要因のうち、いずれか一つ、あるいは複数が重なって発生した可能性が高いと考えられます。
今後の警察および労働基準監督署による詳細な現場検証と関係者への聞き取りにより、事故の全容が解明されることが待たれます。
この悲劇を繰り返さないためにも、徹底した原因究明と、事業所における一層の安全管理体制の強化が求められます。

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。