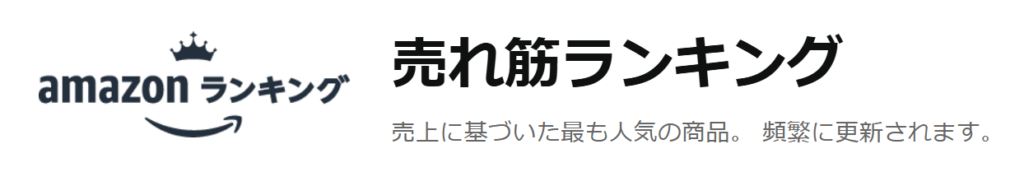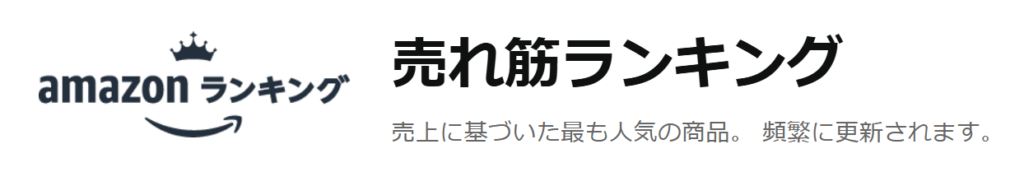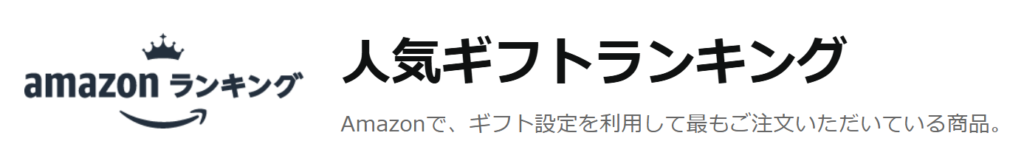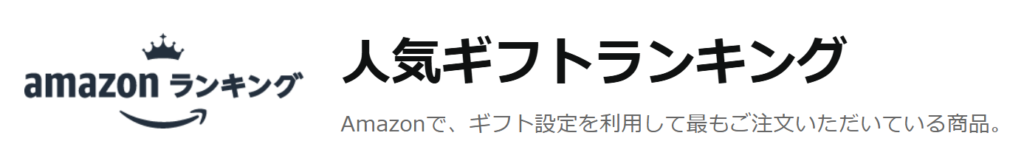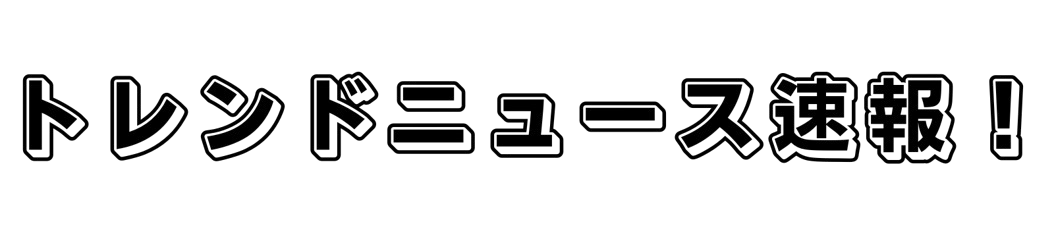東京都出身の鈴木憲和農林水産大臣が、なぜ選挙区に山形を選んだのか。
その背景には、家族のルーツと、日本の農業や地方が直面する課題への強い問題意識がありました。
キャリア官僚という安定した道を離れ、縁のある地で政治家としてのキャリアをスタートさせた選択の裏側を探ります。
- 鈴木憲和氏が選挙区に山形を選んだ核心的な理由
- 父親の故郷・山形県南陽市との深いつながり
- 農林水産省の官僚から政治家へ転身した背景
- 地盤ゼロから山形で支持を築いた経緯
鈴木憲和が「山形」を選んだ理由:父の故郷と農業への信念

鈴木憲和氏の経歴を見ると、東京都中野区で生まれ育ち、私立開成高校から東京大学法学部に進学、そして農林水産省に入省という、いわゆる「エリート街道」を歩んできました。
しかし、彼が政治の道を志したとき、その舞台として選んだのは出身地の東京ではなく、山形県でした。
この選択には、大きく分けて二つの理由が存在します。
一つは「家族のルーツ」であり、もう一つは「官僚時代の経験」です。
理由1:父親の故郷・南陽市への愛着
鈴木氏が山形県と強いつながりを持つ最大の理由は、
であることです。
鈴木氏自身は東京で生まれ育ちましたが、幼少期から夏休みなどを利用して、父の故郷である南陽市を頻繁に訪れていました。
その中で、都会の生活とは異なる山形の豊かな自然や、地域の人々の温かさ、人のつながりの深さに触れて育ちました。
本人も

父のふるさとは、子どものころから親しみがあった土地
と語っており、この原体験が彼の中で山形を特別な場所、すなわち「第二のふるさと」として意識させることになります。
政治家を志すようになった際、この幼い頃からの愛着が
「父のふるさとに貢献したい」
「この地域をもっと元気にしたい」
という純粋な動機へとつながりました。
彼にとって山形は、単なる選挙区ではなく、自らの血縁と心のよりどころが結びついた場所だったのです。
理由2:農林水産省で直面した「現場」の課題
鈴木氏が山形を選んだもう一つの決定的な理由は、彼の前職である農林水産省での経験にあります。
東京大学を卒業後、2005年に農林水産省に入省した鈴木氏は、キャリア官僚として日本の農政の中枢に身を置きました。
霞が関で政策立案に携わる中で、彼は大きな壁に直面します。
それは、「机上の政策」と「現場の実態」との間に存在する大きな隔たりでした。
中央官庁で練られる政策が、必ずしも地方の現場が抱える深刻な問題の解決に直結していないのではないか。
地方が直面する構造的な問題、特に農業分野での担い手不足や、手間をかけても十分な収入にならない「儲からない」という現実を痛感します。
鈴木氏自身が役人時代に畑を借りて農業を体験したこともあり、その難しさと課題を肌で感じていたとされます。
この「現場の声が届かない」というもどかしさが、次第に
という強い決意へと変わっていきました。
そして、その「現場」として彼が選んだのが、父の故郷であり、日本の主要な農業地帯の一つでもある山形だったのです。
農業政策への強い思いが、彼を山形へと導きました。
なぜ地盤のない山形だったのか?ゼロからの挑戦と現場主義


自らの信念に基づき山形での出馬を決意した鈴木氏ですが、その道は決して平坦なものではありませんでした。
そこには、政治家としてのキャリアを築く上で最も困難とされる「地盤ゼロ」からのスタートが待っていました。
安定を捨てた決断:2012年の山形移住
2012年2月、鈴木氏は7年間勤務した農林水産省を退職します。
そして、父の故郷である山形県南陽市へ家族とともに移住しました。
通常、国政選挙に出馬する場合、親から受け継いだ「地盤」(後援会組織や知名度)があるか、あるいは長年その土地で活動してきた実績があるのが一般的です。
しかし、鈴木氏にはそのどちらもありませんでした。
父親の健司氏は南陽市の出身ではあるものの、政治家ではなく一般の会社員とみられています。
そのため、鈴木氏には選挙活動を支える後援会組織も、地域での圧倒的な知名度もありませんでした。
まさに
からの挑戦でした。
安定した中央官僚のキャリアを捨て、縁故が強いとされる地方の選挙区に、何の保証もないまま飛び込むことは、非常に大きなリスクを伴う決断でした。
地道な活動で築いた信頼
政治基盤が全くない鈴木氏が頼れるのは、自らの情熱と行動力だけでした。
2012年の移住から同年12月の衆議院選挙までの約10ヶ月間、彼は徹底した「ドブ板選挙」とも呼ばれる地道な活動を展開します。
選挙活動には数千万円の費用がかかり、約2000枚のポスターを用意したとされています。
彼は長靴を履き、来る日も来る日も選挙区内(山形2区)の家々を一軒一軒訪ね歩きました。
畑や田んぼで農作業をする人を見かければためらわずに声をかけ、地域の集会やイベントには積極的に顔を出し、ひたすらに自分の政策と山形への思いを訴え続けました。
最初は「東京から来た若者」「官僚様」と距離を置いて見ていた有権者も多かったと推察されます。
しかし、都会出身であることを隠すのではなく、むしろ真摯に



父の故郷のために働きたい
と訴え、地元の声に耳を傾け続ける鈴木氏の姿に、少しずつ信頼が寄せられていきました。
その結果、2012年12月の第46回衆議院議員総選挙において、強豪ひしめく山形2区で見事に初当選を果たします。
この地盤ゼロからの勝利こそが、彼の「現場主義」という政治姿勢の原点であり、現在の強固な支持基盤の礎となっています。
鈴木憲和の政策と山形への視点


初当選から現在に至るまで、鈴木氏は一貫して山形に拠点を置き、政治活動を続けています。
彼の政策には、官僚時代の知見と、山形で培った「現場感覚」が色濃く反映されています。
「現場主義」を貫く政治姿勢
鈴木氏の政治信条は「現場主義」に尽きると言えます。
当選後も地元の人々との対話を何よりも大切にし、農業イベントや地域行事への参加を続けています。
その姿勢を象徴する出来事として、2016年のTPP(環太平洋パートナーシップ協定)関連法の採決において、党議拘束に反して退席したことが挙げられます。
これは、党の方針と地元の農業関係者の懸念との間で悩み、最終的に「現場の声」を優先しようとした行動とも解釈でき、彼の政治家としての覚悟を示すものとなりました。
こうした現場重視の姿勢と農政への深い知見が評価され、キャリアを重ねていきます。
外務大臣政務官、自民党青年局長、農林水産副大臣、復興副大臣といった要職を歴任。
そして2025年10月、高市内閣の発足に伴い、第73代農林水産大臣に就任しました。
山形から日本全体を見据える政策
農林水産大臣となった今、鈴木氏の視線は山形という「現場」から、日本全体の未来へと注がれています。
彼が公式サイトなどで掲げる政策(DB情報に基づく)は、地方が直面する課題を解決することで、国全体を底上げしようというビジョンに基づいています。
- 「稼げる農業」への転換「農は国の基本」と位置づけ、米をはじめとする国内農業を守ると同時に、補助金に依存しない「稼げる農業」への構造転換を訴えています。
スマート農業の推進や、国内外への販路拡大(輸出促進)が柱となります。 - 地方資源を活用したエネルギー政策山形が持つ木材資源、雪室(雪氷エネルギー)、小水力発電、太陽光など、地域に眠る資源を最大限に活用した再生可能エネルギーの導入を推進しています。
- 地方の雇用創出と子育て支援中小製造業の技術革新支援や、地方での起業サポートを強化し、若者が地元で働き、消費できる環境づくりを目指します。
また、自らも二児の父親としての経験を活かし、「出産・子育て環境ナンバーワン」を掲げ、地域社会全体で子育てを支える仕組みを提唱しています。 - 「山形の声」を中央へ彼の根本にあるのは、「地方の実情を中央にぶつける」という強い意志です。
大都市の論理や霞が関の論理だけでは、地方の課題は解決できないという信念のもと、現場の声を国政に反映させることを自らの使命としています。
東京出身でありながら、父の故郷である山形に根を下ろし、農業と地方の課題解決に挑み続ける鈴木憲和氏。
彼のキャリアは、地縁や血縁を超え、自らの信念と情熱によって「ふるさと」を選び取った政治家の一つの姿を示しています。
まとめ:鈴木憲和はなぜ山形から出馬?東京出身で選挙区を選んだ2つの理由
- 鈴木憲和氏が山形を選んだ最大の理由は、父親の故郷(山形県南陽市)であったこと。
- 農林水産省の官僚時代に感じた、地方や農業の課題を現場から解決したいという強い思いも背景にある。
- 2012年に山形へ移住し、政治的「地盤」が全くない状態から活動を開始した。
- 一軒一軒を回る地道な対話と現場主義の姿勢で有権者の信頼を獲得し、初当選を果たした。
- 農林水産大臣に就任(2025年10月)した現在も、山形を拠点に「地方からの国づくり」を掲げている。



今後のご活躍を期待します。